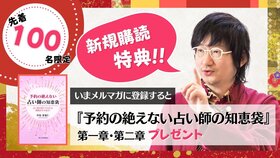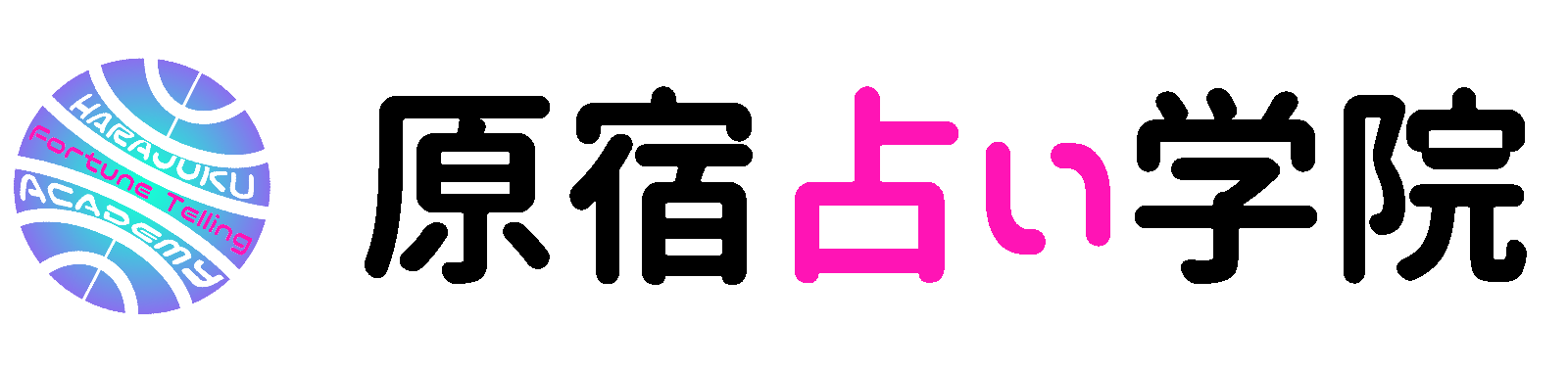昨日のYouTube生配信では、『占い師一本で稼ぐための極秘アドバイス』をテーマにお話ししました。
まだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてください。
👉 動画はこちら
そして、何か感じたことがあれば、コメントもお待ちしています!
「先生」という呼称は、ある種の“演出”
占い師は医者でも弁護士でもないのに、「先生」と呼ばれることが多いですよね。
この呼称、実はある種の【演出】。
といっても、お客さまを騙そうという意図ではありません。
相談者は「誰にも言えないけど自分では解決できない悩み」を抱えて占い師のもとを訪れます。
そのため相談者は、占い師に『権威』を求めるのです。
「先生」と呼ぶことで、「この人なら自分の悩みを解決してくれるかもしれない」という期待値が高まります。
一種のプラシーボ効果のようなものですね。
プロは「先生」という言葉の意味を知っている
ベテランの占い師は、この理屈をよく知っています。
なのでプロの占い師は、他の占い師のことを先生と呼びませんし、同格の占い師から「先生」と呼ばれたら、
「あらやだ。私はあなたの先生じゃありませんからサン付けで呼んでくださいね」
と、スマートに切り返すのです。
その自然なそぶりが、また器を大きく見せるわけです。
一方で、駆け出しの占い師はその理由を知らないまま、「先生」と呼ばれることで、自分が偉くなったような錯覚に陥ってしまうことも。
「先生」の語源は“先に生まれた人”
そもそも先生の由来は『先に生まれた人』という意味。
論語にもある孔子の言葉「後生畏るべし(後に生まれる者を恐るべし)」に対する後生(コウセイ)の対です。
そこから、学芸の優れた人を指し、政治家、弁護士、医者、教師、芸術家、作家、美容家など、偉い人や優れた人を尊敬するため用いるようになりました。
呼称に込められた「責任」と「品格」
占い師が先生と呼ばれるのはあくまでも相談者や生徒からです。
また、運営側もあえて「先生」と呼称しますが、それには理由があります。
「相談者に対してちゃんと責任を持って高尚な鑑定をしてくださいね」
「あなたは先生なのだから素人のような発言はしないでくださいね」
という意味合いが、込められているわけです。
一方で、「先生」と呼ばれることを嫌がる占い師もいます。
呼称によって、感覚が麻痺して慢心することを警戒するからです。
学校の教職員は、いわゆる公務員なので、本質的な「先生」ではありません。
しかし、幼い子どもを指導するので、権威性を持たせる「先生」という呼称は、それなりの効果がありますが、心から尊敬されているとは限らない――。
その現実を占い師も自覚しておく必要があるのです。
「先生」が魅せる“おもてなし”
「弁護士でも医師でもない一介の占い師が“先生”などと呼ばれるのは片腹痛い」
と考える人もいれば、「恥ずかしいからやめてほしい」という人もいます。
先生と呼ばれて、有頂天になる人はたしかに多いです。
また、呼ばれ慣れているとそれが普通になって、「なぜ先生と呼ばないんだ」となってしまう人もいます。
結論的には、相手がどう呼ぼうが、それは相手の自由です。
尊敬の気持ちで「先生」と呼ばれたなら、ありがたく受け取ればいいのです。
尊敬されて本心から「先生」と呼ばれる占い師は、その見た目や所作にも気を配っています。
独特な髪型をして、威厳のある衣装を身にまとうのは相談者やファンに対しての “おもてなし”の一部なのです。
医者の白衣や弁護士の記章と同じで、いわゆる権威性を雰囲気で示すアイテムです。
占い師…その独特な世界で長く成功していくためにはこういうプロ思考が必要となるのです。