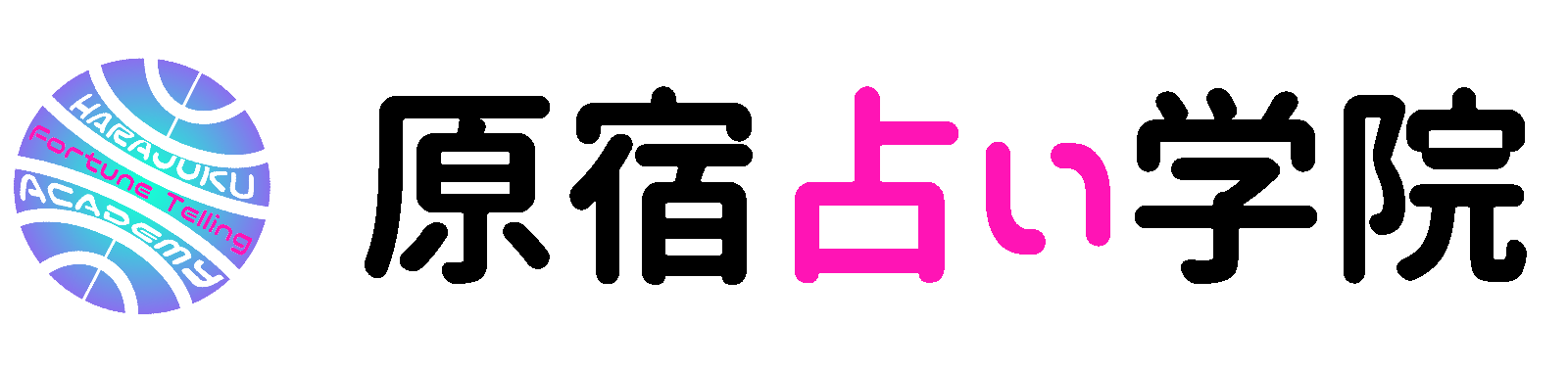YouTube配信のお知らせ
先日はYouTube生配信で陰陽と五行について1時間ほど喋りました。
こちら、チャンネル登録はもちろん、ぜひとも高評価と、コメントを残してくださいね!
配信はこちら
五行の法則と食養生
五行の法則から食材と臓器が割り出せますし、さらに感情や事象の分類もできます。
足りない五行を食材で補い、多い五行の食材を控えることで運がメキメキと上がるのです。
なぜ開運するのかというと、臓器と感情のバランスが整うから。
五行のバランスを整える
例を挙げると…
「木」の気が不足していれば、「木」の食材を取り入れる。
「火」の気が多すぎれば、「火」の食材を控える。
とってもシンプルな方法ですが、正確には複雑なシステムです。
なぜなら「五行」というのは単体では成り立たないからです。
循環の前提と人体との共通点
この五行の法則は「循環すること」を前提に作られています。
互いに支え合って、絶妙なバランスを維持している。
人間の臓器や体の部位だってそうですよね、単体では成り立ちませんから。
それぞれの器官が、消化⇒吸収⇒循環⇒排泄⇒代謝という役割を果たして、人体を維持しているわけです。
なので、ひとつの部位に異常がでれば、他の部位にも間接的に影響が出ます。
これは、改善する場合にもいえますよね。
全体バランスを意識した養生
もちろん、ピンポイントで改善できる場合もあります。
でも、たいていは他の五行への影響も配慮する必要があります。
たとえば、
「最近怒りっぽい」
あるいは、
「肝臓の数値が思わしくない」
そういうときは五行の「木」が弱っていると判断するわけです。
セオリー通りなら「木」の食材を摂って補えばいい。でも、ひとつ注意点があるんです。
「木」の五行には…
「水」の気を逃がし、
「火」を強める作用があり、
「土」の力を抑え、
「金」からの攻撃を受け止めるといった役割もあるんです。
つまり、
ひとつの五行を補うことで、すべての五行にも間接的な影響を与えるわけです。
だから、
全体のバランスを考慮しながら改善する必要がある。
これが「五行」の奥の深さでもあり面白さでもあるんです。
どの五行が崩れているか?
問題は、どの五行バランスが崩れていて、それをどう見極めるかですよね。
さらにいえば、多すぎて弱っているのか、少なすぎて調子が悪いのかなども判断する必要がある。
もちろん、自覚症状で判断するのもひとつの方法ですが、あくまで自分の感覚だといまいち信憑性に欠ける。
四柱推命による五行分析
そこで登場するのが四柱推命という占術です。
この四柱推命の本質は『扶抑法(ふよくほう)』という五行の強弱を「数値」で表せるとても便利なシステムなのです。
食の好みや普段の摂取量である程度判断できます。
好きな食べ物っていうのは意識しなくても多く摂りすぎます。
大好物が牛肉でなら、「土」の要素が過剰で、胃が弱っている可能性が大きい。
苦みの強いピーマンが苦手なら、「火」の五行が不足しているはず。
こんな感じで「五行」の強弱を目算することができるのです。
まとめ:試してみてほしいこと
ちょっと複雑ですが、分かってしまうと単純な理論です。せっかく占いを勉強したのなら開運する食養生を試してみて。
プロ占い師として、ワンランク上の鑑定ができるからお客さんに喜ばれるはずです。